ブルーロックの向こう側へ
これは何
最近読んだ本・漫画の感想、弊社のミッション、現在の弊社の(というか俺の)怪文書業務についてお話しします。

1. 「"できる"は状態である」という発見
先日『働くということ 「能力主義」を超えて』を読んだ。めちゃくちゃ面白かった。俺の嫌いな「働く」について、考えが深まった。
この本のキモは、「何かを "できる" のって、その人の生まれつきの性質じゃなくて、その時々の状態なんだよ」という部分にある。
転じて、「あいつは"できる"やつだ」という能力主義的判断によって見逃される「"できる"状態」を大事にしましょう、と言っている。
じゃあ、その「"できる" 状態」って何かっていうと、「その人の個性と、周りの環境(仕事内容とか、評価のされ方とか)との関係が、うまく噛み合っている時に生まれるもの」らしい。
この考え方でいくと、個人レベルでは、「自分・他人は"できる"/"できない"」と決めつけて一喜一憂する前に「どうしたら自分や他人が "できる" 状態になれる?」と考えるのが大事だよねということになる。
こっちのほうが自分にも他人にも寛容で HAPPY な感じがする。
2. 例:ブルーロックの潔くんムーブ(※環境はダメ)

で、この「"できる"は状態であり、関係性の中で生まれる」ってのをわかりやすく伝えるために、漫画『ブルーロック』の主人公、潔世一(いさぎ よいち)の話をします。
『ブルーロック』は、世界一のストライカーを育成するためのプロジェクトを舞台として、参加者の高校生たちが特殊な環境下で競い合うサッカー漫画デス。
すみません、俺は頭がおかしいので、何でも漫画に関連させて考えてしまいます。
『ブルーロック』って、才能あるエゴイスト達が競い合って、勝ったやつだけが生き残るというプロジェクトを舞台としておるんで、能力主義的な思考に囚われやすそうな環境じゃないですか。
でも、主人公の潔の成長を見てみると、彼はむしろ(一元的にできる / できないを測るような)能力主義に囚われないことで成長を続けているように見える。
潔クンは、周りの人の強みとか考え方(=エゴ)を観察して、自分なりに再構成して、チームメイトや対戦相手との関係性の中で独自の武器を手に入れていっておる。
そうやって「"できる"状態」を更新し続けておる。
まさに、「関係性の中で "できる" 状態が生まれる」を体現しているように思うんスよね。
3. 「やさしいブルーロック」欲C
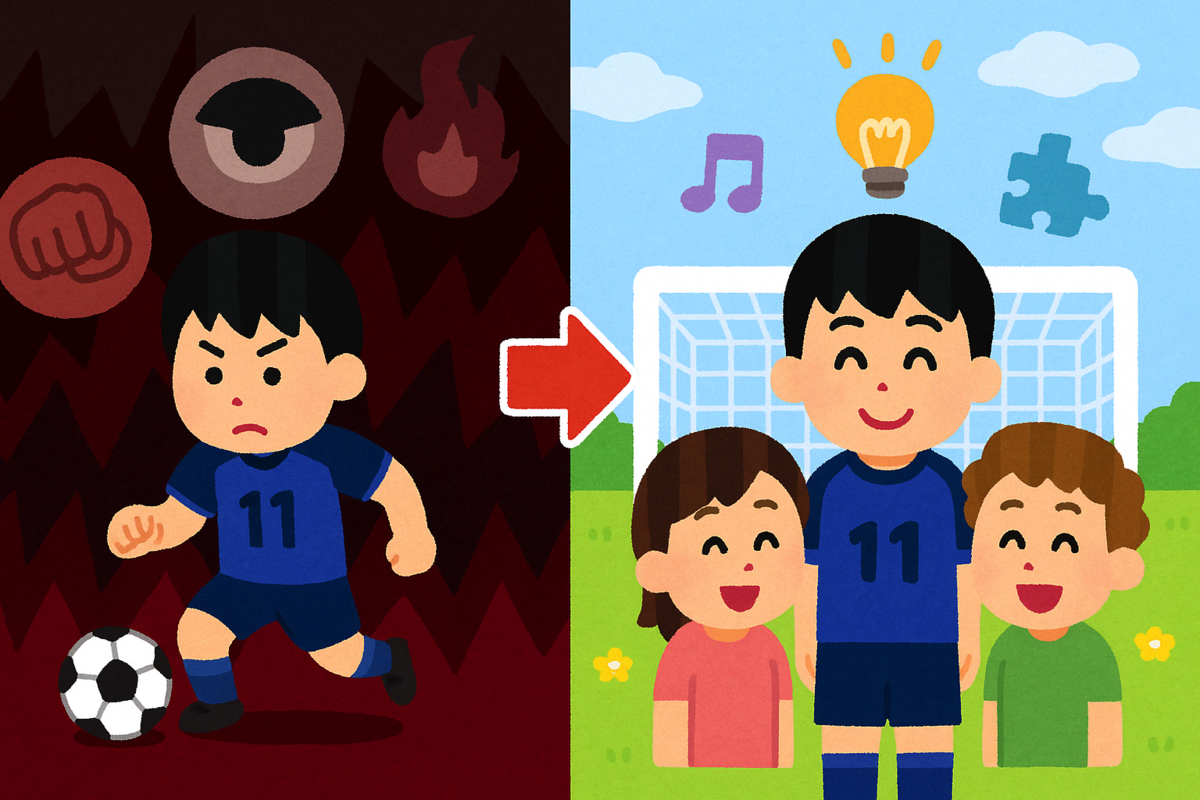
『働くということ』は、(乱暴に言うと)まさにこの潔くんみたいな動き方を推奨していそう。
つまり「周りとの関係性の中で、自分の"できる"状態を更新していく」ような働き方や。
固定化された「能力」で評価され選抜されるのはキツすぎます。
そうではなく、変化する状況や人間関係の中で、「今の自分には何ができる?」「どういう関わり方ができる?」と流動的に考えられた方が、精神衛生上よろしい気がする。
ただし、ブルーロックは潔を生み出すために極限プレッシャーかけており、これは実社会でやるとヤバすぎる。今は令和なので。
「潔ムーブ」を、もっと(心理的に)安全な状況で、多くの人が自然にできるようになるのが一番嬉しいということになる。
「やさしいブルーロック」とかいう存在しないものが欲しい。
4. 弊社のミッション

この「やさしいブルーロック」は、存在しにくい点に目を瞑ると、かなり良い。
単に個人が楽になるだけじゃなくて、たぶん組織とか社会にとっても良さそう。
メンバーが自律的に新しい「"できる"」を見つけてくれたら、組織としても新しい価値が生まれたり、変化に対応しやすくなったりして嬉しいはずなんで。
また、お互いを固定的な「能力」で見るんじゃなくて、「今はこういう関わり方ができるな」って流動的に見れれば、組織内の構成員間で寛容な関係性が築けそうなんで。
今から会社に魂を売ります。
じゃあ、どうやったらそんな都合の良い状態に近づけるのか?
そこで大事になってくるのが、「採用におけるマッチング」なんじゃないすか。
「個人が潔のように振る舞えるか」って、その人の特性だけじゃなくて、「その人が置かれる環境(組織文化、チームメンバー、仕事内容とか)との相性」にめちゃくちゃ左右されるんで。
個人と組織が、お互いにとって「"できる"状態」を引き出し合えるような「最高の組み合わせ」を見つけることが大事なんスねえ。
ここで、HERP とかいう会社は「採用を変え、日本を強く。」をミッションとして掲げておる。
「この会社だから、この人は活きるな」「この人が加わったから、この会社はもっと面白くなるな」という強いコンボが採用を通じて発生すると良いですねという話です。
俺たちは「やさしいブルーロック」が発生するように採用業務を変革していきますということです。
弊社は新メンバーを募集しているので、ブルーロックが好きな人はぜひ採用情報をチェキしてください。
魂を買い戻しました。
5. この文章は一旦何だったのか???
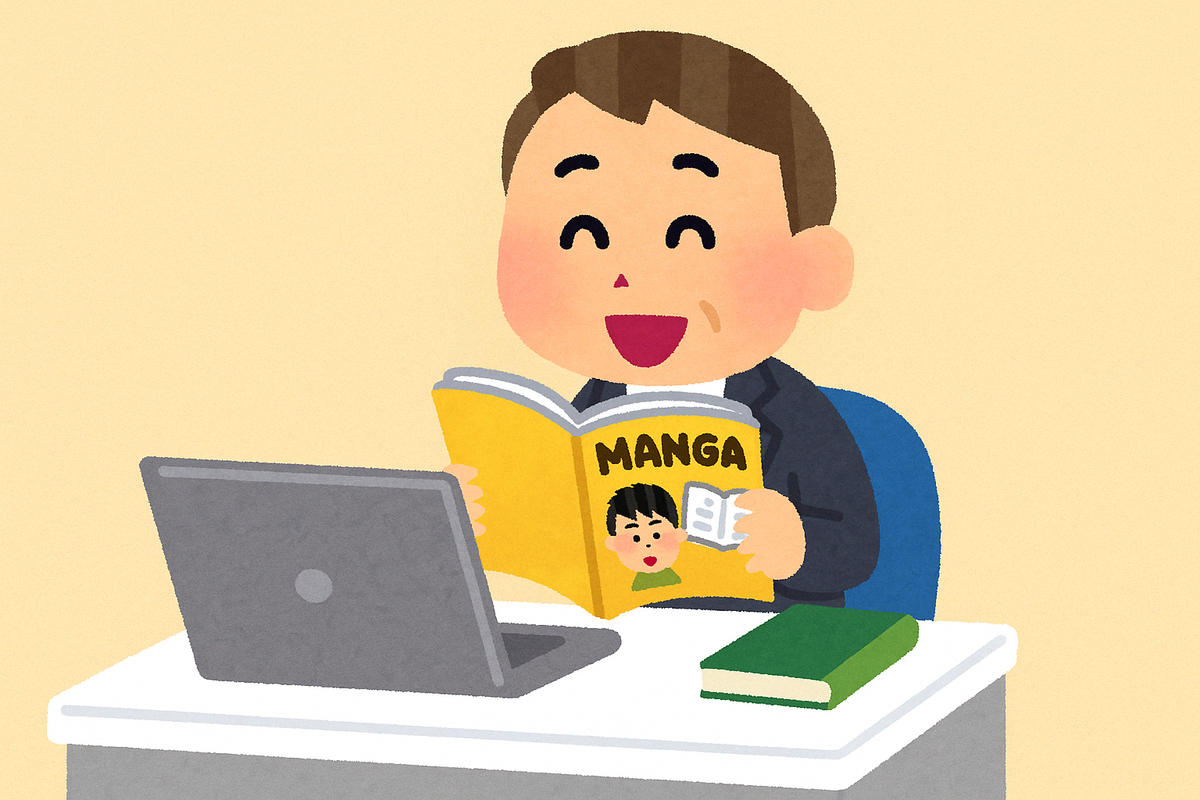
本と漫画の感想を書いて給与発生したら嬉しすぎるので、そのようにした。
流石に本当に本と漫画の感想しか書いていなかったらヤバすぎるため、弊社のミッションのお話をオチにした。
皆さんは弊社のミッションへの理解を深めたはずです。
今のところ「自称漫画評論家おじさん」をしても会社で怒られていないので、得だ。
現在弊社では「なんでも良いから会社の名前使ってインターネットに記事が公開されてるのが大事じゃねーか!?」という意識があり、謎の漫画評論家おじさんが許されている。
「今後はインターネットに流す記事の方針もお上が決めるようにしましょう」という話もあり、そうなると謎の漫画評論家おじさんは失業する。
今のうちにスタートアップ企業で漫画評論してお金もらいたい人も是非採用情報をチェキしてください。
"自称漫画評論家おじさん" という職種ではないです、念の為。